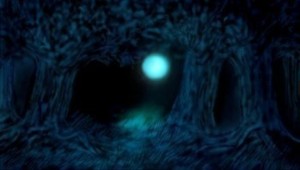
王子の小鳥
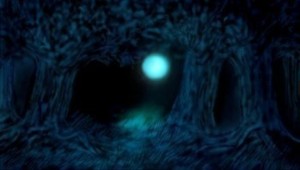
轟々と唸る風に、雲という雲は吹き流され、晩秋のわびしい夕陽が枯れ草のそよぐ荒野を陰気に照らしつけていた。
野を歩いてきた男があった。男は、呪いの手のような枝葉で空を引っかいている大樹に這うようにして近づくと、その根元に今宵の宿を求めた。
背負っていた荷をおろし、辺りに落ちている枝を拾い集めて、懐から取り出した火打ち石で小さな焚き火をおこす。風雨によって
板のように硬くなり、色のあせた外套をしっかりと引き寄せると、幹に凭れて坐った男は荷袋の口紐をほどいた。
「こんなところで今晩休むつもりなの」
真上から声がした。
男が見上げると、絡み合った枝のはるか上の方に、少女の姿があった。
少女は男ものの服を着ており、狩りの帰りなのか、その背には弓と矢筒を背負っていた。あまりにも高い処にいるので、下から見ると、小さな鳥か獣くらいの
大きさに見えた。
風はもう止んでいた。少女は腰をかけていた枝の上に立ち上がると、まっすぐに腕を伸ばし、地平の一点を指さして、下にいる男に教えた。
「この先に村がある。日が暮れるまでには辿り着ける。そこでなら、あたたかな食事と酒が手に入る」
「結構だ」
男はもう少女に構わなかった。途中の川から汲んできた水筒の水を鍋にうつし、穀物と乾燥肉を落とし込む。
携帯している貴重な胡椒や香草を外套のかげで包みなおし、残りの食料を油紙と布で一まとめにしてしっかりと結わえ直すと、火を加減して、
気長に煮立つのを待った。その一部始終を少女は興味深そうに上から見ていた。
「森の中でこの木がいちばん立派で背が高い」
どことなく誇らしそうに、やがて少女が口をきいた。
それまで黙っていたのは、食事の用意をしている男の邪魔をしたくなかったからのようだ。少女というよりは、快活な少年のような口の利き方をする。白い湯気を
立てて鍋の中で穀物と肉がやわらかくなってくると、男は木の上にいる少女に声を掛けた。
「降りてきて、一緒に食べるといい」
長い間ひとりで旅をしてきたせいで、自分の声とも思えぬ、しゃがれ声に聴こえた。少女はさっと木からおりてきた。木登りは登る時よりも降りる時のほうが怖いというが、
普段からよくこの木に登っているものか、高みから地上まですべり降りるようにして、少女は一度も掴む枝を迷ったり、足場を探したりはしなかった。
少女は男の前に降り立った。
言葉遣いと少年のこしらえでいかに誤魔化しても、それは野の花のように可愛らしい少女だった。可愛いと思うのは、男がしばらく女を見ていないからと
いうだけではない。好奇心と自立心を秘めた双眸をしており、その頬は白桃のようにすべらかで、小さな唇は紅を塗らずとも赤く、華奢なからだつきに
少年の服がよく似合っていた。
「狩りをするには獲物の見当たらぬ、寂しいところだ」
「狩り。ああ、これのこと」
男のように脚を組んで坐ると、少女は弓と矢筒を大樹の根において、悪戯っ子のように、ふふふと笑った。
「狩りをしようと思って城を出てきたのではないのです。こう見えて、弓は結構使えるのだけど」
城、と少女が云ったことに男は耳をとめた。
都で流行の美女の基準の箇条書きに照らし合わせるならば、やせっぽちの少女は女の魅力にはとうてい足りず、その髪も、もっとも厭まれる赤毛で
あったが、そういった既成概念を吹きとばすほど、男装の少女はのびやかな若さと瑞々しさに満ちていた。
「お城に用なの?」
少女は男を見つめてそう訊いた。それが癖なのか、口の端をほんの少し吊り上げていた。少し皮肉めいてみえる笑顔だった。
「ああ。そうだ」
男はうっそりと木匙で鍋をかき回した。男は嘘をついた。男にはこの少女が誰であるか、分かったのだ。
「噂に名高い王子の小鳥。このような処で逢えるとは思わなかった」
「小鳥ねえ。一の従者だと自負しているのだけど!」
そこには、少女らしい切実な不満が篭っていた。
食事ができあがると、何か珍しい話をきかせて欲しいと少女は男に求めた。男は海の話をしてやった。
「故郷だ。海辺の村で生まれた」
生まれた村で生き、その村から一歩も出ぬままに死ぬ者がほとんどの時代において、内陸の人間にとっての海とは、想像を絶する奇観であった。
海育ちの旅人の話に少女はすぐに惹き込まれた。
「湖がたくさん集まっているようなものかな」
「違う。喩えるなら、この荒野一面が水なのだ。舟を漕いで行っても、ずっと果ての果てまでだ」
「それでは、人は何処に住んでいるの」
「陸地とは、海の間に浮かんでいる島なのだ。島の大きなものが、大陸だ」
「では、この大地も」
「地表を流れる河はすべて海に流れ着く。しかし海の水は、井戸水や川の水とは違って、塩辛い。神の怒りをかった船乗りたちが
海底の牢獄で流している涙が混じっているからだ」
「涙が」
王子の小鳥。それが、この少女のひろく知られたあだ名であった。そこに涙が伝い落ちてでもいるかのように、少女はおのれの頬に手をおいて考え込んだ。
眉唾そうに、しかし信じないでもないような顔をして、王子の小鳥は男の話を熱心に聴いた。
「城に帰らなくてもよいのか?」
男の問いに、木の碗によそった煮込みをすすりながら少女は首を振った。空はすっかり暮れて、雲のない藍色の天蓋と変わり、
金貨のような星と銀貨のような月が寄り添っていた。
「久方ぶりに閑が取れたのです。狩りに行くと云って城をとび出してきた。王子ときたら、あれはするな、これは危ないと、いつも私から愉しみを奪おうとするのだから」
「それは、御身のことを心配しておられるからだろう」
少女はおもむろに大樹に立てかけていた弓を取り上げて、それを膝に抱えると、俯き加減に弓弦を指ではじいた。
「女の服を着せようとするし」
「着たらいい」
「着てみた。宴の余興として、王と王妃もそう思し召しだったから、断れなかったのです」
「城の方々も、お喜びになっただろう」
「とんだ道化でした。城には、とても美しい金髪の姫がいるのです。同じ年なのに私と姫が並んだところときたら、まるで石と薔薇」
そのわりには、弓弦をはじく少女の口調は暗くなかった。
「王子だけが、妹よりも、私のほうがいいと云ってくれた。お世辞というよりも、あれは慰めだったけれど」
「本気だったのでは」
男はついつい少女をからかう気になった。知らぬ者はいないではないか。その国の王子はいつも赤毛の少女を従者として伴っていて、実の妹姫よりも身近にしていると。
こうして少女の実物の姿を目の当たりにしていると、吟遊詩人たちが歌うその国のことが男にも想像できた。緑に染まる城の中庭で、王子とこの娘が語らっている情景も。
「王子のことをどう想っているかだって。旅のお方までそんなことを」
男の問いをはぐらかえし、少女は余所見をした。
「世継ぎの君として申し分ない御方です。好ましくお仕えしています。周辺諸国の殿方のように、女と戯れてばかりいるような軟弱な方ではありませんし」
「王子はあなたを贔屓にして、片時も傍から離さぬのだとか」
「大げさな。私は王子の従者です」
少女はきゅっと唇を閉ざした。その横顔を、焚き火が淡く照らした。
翌朝、まだ空が薄暗い頃に、男は眼をさました。
少女の姿はなく、焚き火は消えており、夜露に濡れた草がそよぐ荒野は夜明けを知らぬ海底のように静まっていた。男は枕にしていた荷を背に背負うと、
朝風の中に歩き出した。
木の上から少女が「この先に村がある」と教えた方角には、廃村しかないことを男は知っていた。
雲間から薄日のさす昼近くなって、幸運にも僻地に暮らす農夫と出くわし、男は農夫と値段を交渉して痩せた老馬を譲り受けた。今まで乗っていた馬は、三日前に
脚をくじいて死んでしまったのだ。
廃墟を遠目にみながら、男は古い街道に馬をすすめ、その日の夕方、ようやく目指す町に辿り着いた。二晩の野宿の後だったので、宿のたっぷりとした食事と酒が
ありがたかった。
「よそから来た御方には、ぜひこの歌を」
食堂では吟遊詩人が求められるままに土地の歌をうたっていた。
「城にも楽師が来る」
少女は弓を抱えて手琴を弾く真似をした。
「あいつらときたら、お花がどうした恋がどうした、そんな下らぬ歌ばかりで、下女とみれば流し目をくれるのです。大嫌い」
しかし、王子の小鳥は彼らから愛されていた。大嫌いと得意げに云ってのけた少女の笑顔を、男は彼らにも見せてやりたく思った。
「もうすっかり夜だ。方々が心配するぞ」
「そうですね。そろそろ帰ろう。おもしろい話をいろいろと有難う。城の皆にも話してきかせます」
弓と矢筒を手にして立ち上がると、少女は大樹の根を跨ぎ超えた。男は訊いた。
「城の皆さまは、しあわせに暮らされているのだな」
振り返った少女は、いったい何を云うのかといった顔をした。いつまでも胸に残るような笑顔だった。少女の後ろ姿が荒野の闇に消えるまで、男は動かず見送った。
「ええ、私も、王子も、皆しあわせにやっています」
「昔、この近くにひとつの国がございました」
吟遊詩人の口上に、宿に集った人々は耳を傾けた。
「古い塔が夕陽に照らされているのがその名残。「王子の小鳥」の歌。お聴き下さい」
楽の音がはじまった。男は目蓋を閉じた。
野末の廃墟をごらんあれ 見る影もない昔日の姿
風にそよぐはりんどうの花ばかり
昔ばなしをおききなさい 七日七晩の戦いのはてに抗う力はもはやなく
王と騎士は塔より出でて ひろき野に屍となり果てぬ
それを見届けたは城のもの
王妃は姫君たちと高き塔より身を投げて
小国は炎の中に滅びゆく
昔ばなしをおききなさい 王子の小鳥と愛された赤毛の娘
その最後の最後まで弓矢をはなって王子をまもり
運命を共にしたのだよ
風にそよぐはりんどうの花ばかり
やがて城址も消えてゆき
風に残るはこの音色
[了]
あとがき
Copyright(c) 2009 Yukino Shiozaki all rights reserved.